
8巻に入って、物語が大きく動いた「大奥」。自分のなかでは過去最高の面白さで、12月にはもう次の巻が出ちゃうなんてうれしすぎる。
そして今回は、初の料理が登場するエピソードもあって、よしなが先生の食べ物描写が好きな身にはたまらない巻でもありました。

※【コマ引用】「大奥」(よしながふみ/白泉社)8巻より
江戸一の料亭「かね清」で、唯一の男の料理人として腕をふるっていた善次郎。
「女の職場」に男がいると場が乱れる――という理由で店をクビになり、板長のはからいで、「男ばかり」の大奥の御膳所で働くことに(このへんのジェンダー逆転シチュエーションが、この作品ならでは)。
入ってすぐ、お決まりの新人いびりとして、大量の里芋の下処理を命じられますが、もともと腕のいい善次郎はあっという間にこなし、ついでに一流料亭仕込みの煮物の作り方まで披露します。 善次郎が解説するこの煮物のレシピ、江戸時代の、ひいては大奥の食事情が垣間見えてなかなか興味深いです。作中の説明を参考に再現してみることに。

作り方:
里芋はなるべくたくさん用意します(今回は20個くらい)。作中でも大量に作ってたし……ってだけではなく、少量だと里芋のぬめりがあんまり生かせなかったので。皮をむくと案外小さくなっちゃいますしね。

泥をおとした里芋の皮をむいていきます。私のスキルが足りずキレイにできなかったけど、いちおう六方むき風に……。
しかしこんなに大量に里芋をむいたことってなかったので、途中で手に猛烈なかゆみが。ぐあー。 むくのは大変だし、手はかゆくなるし、やっぱり厨房の新人イジメには里芋が一番だぜ!と、なんか納得してしまったほど。


里芋を煮るには鰹節の二番出汁を使います。 二番出汁とは、一番出汁をとった後の鰹節を水に入れて強火にかけ、沸騰させたのち弱火でじっくりとった出汁のことらしい。 ※詳しいひき方はこちらを参照(今回は昆布ナシで)


鍋に里芋を入れて、二番出汁をひたひたに注いで火にかける。弱火で落とし蓋をし、竹串がすっと入るまでやわらかくなるよう煮る。

普段はここで酒、みりんなど使うところですが、今回の味付けは砂糖と濃口醤油のみ、とザッツシンプル。
みりんはこの頃は飲酒用で、調理用に使われるようになったのは江戸後期のあたりからだとか。へーー。
このほかにも、善次郎の調理方法に「煮物に砂糖を使うなんて」と周囲が驚いたり、通常は「下り物の薄口醤油」が使われているのが伺えたり、大奥の特殊な厨(くりや)事情が垣間見えて、ワクワクしてしまうシーンです。同じ江戸にあれど、庶民の台所とはかなり異なっていたのでしょうね。

しばらく煮詰め、そのまま冷まして一晩置く。翌日再度火にかけ、煮返すように仕上げて完成。 食べる直前に柚子の千切りを添える。

食べた感想:
里芋のねっとりした食感としっかり甘辛い味付けは、ザ・関東風の煮物という感じ。ご飯orお酒がほしくなります。ここに柚子の千切りが加わると、ちょっと高級感が出るうえに風味もさわやかに。
この後、善次郎はその腕が認められ、将軍・家重の前で刃傷沙汰を起こして幽閉中のお幸の方と、料理を通して心を通わすことになるのですが、そのエピソードはぜひ本編でお楽しみを(うなぎが…うなぎがむしょーに食べたくなるので注意)。
福田里香先生の「まんがキッチン」での対談のなかで、よしなが先生と福田先生が 「権謀渦巻く『大奥』のストーリーのなかでは、人の「腹の中」を明らかにしてしまうアイテムとしての食べ物を登場させる必要がなかった」 という趣旨のことを語っていらっしゃいましたが、巻が進んで多彩なエピソードが織り込まれることになったいま、こんな興味深い食べ物のシーンが出てきたことに、いちファンとしてうれしく思うのでした。






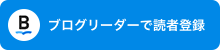




コメント
コメント一覧 (2)
(結構前から、読ませていただいていたのですが・・)
このエピソード、大好きです。権謀術数、どろどろとした大奥の壮大なドラマも好きなのですが、権力を持たない人たちのつましいエピソードは一服の清涼剤のようです。ドラマがついに始まりましたが、こちらも毎週楽しみです。
サトイモ、家人が嫌いなので買わないのですが、自分のためだけに作ってしまおうかと思うくらい、おいしそうです♪みりんを使わない煮物か~
本当に作れるんですね。